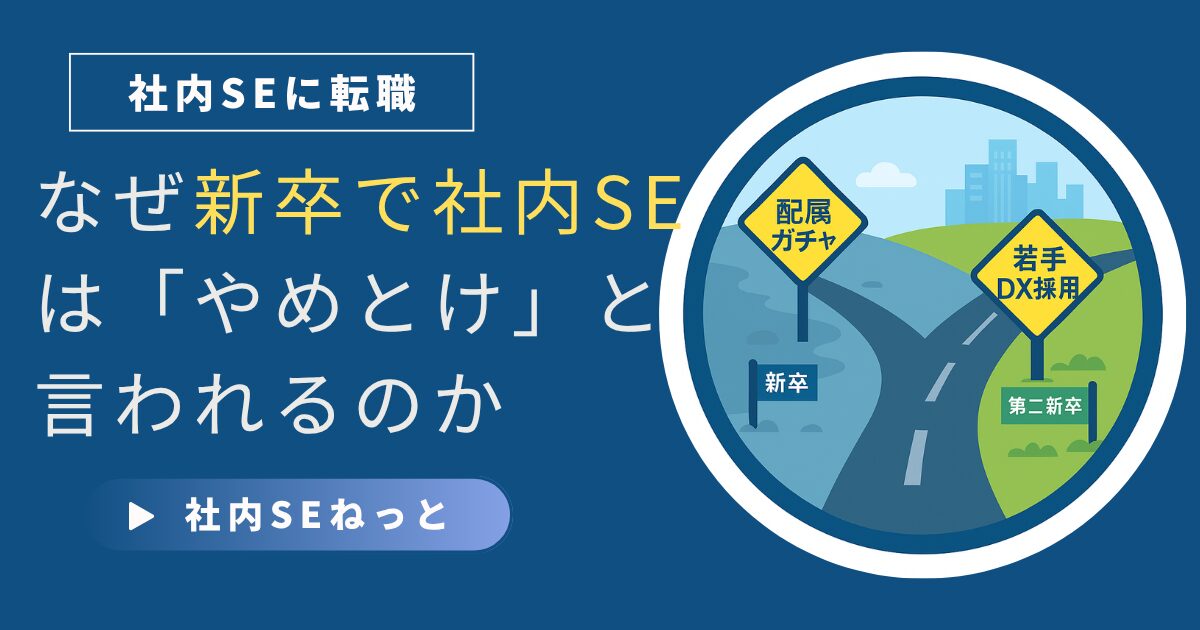新卒・第二新卒としてキャリアの第一歩を踏み出すにあたり、「社内SE」という選択肢に魅力を感じつつも、「やめとけ」というネガティブな評判に頭を悩ませていませんか?
この記事では、まずその不安の正体を明らかにします。結論から言うと、「やめとけ」という忠告は半分本当で、半分は時代遅れです。あなたのキャリアが成功するか失敗するかの分かれ道は、入社する「企業選び」に全てかかっています。
この記事を読めば、「やめとけ」と言われる"ハズレ"企業と、あなたのキャリアを飛躍させる"アタリ"企業を、あなた自身の力で見分けられるようになります。
【共通理解】「社内SEはやめとけ」の真相は?5つの懸念と正しい向き合い方
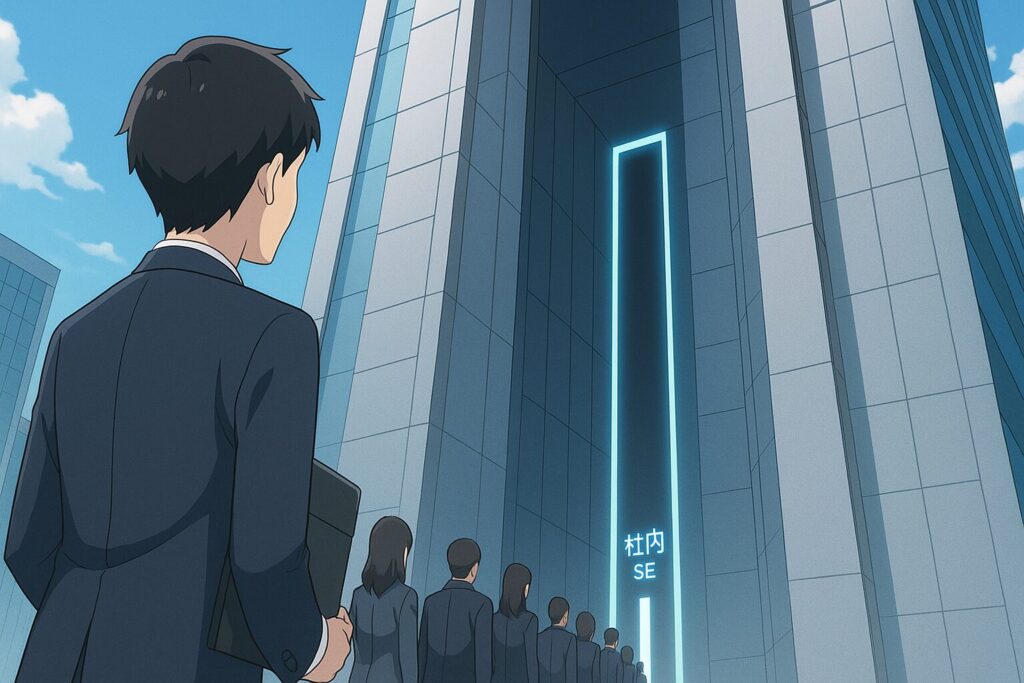
まず、「新卒で社内SEはやめとけ」と言われる際に挙げられがちなポイントを5つの視点で見ていきましょう。これらは必ずしも“ダメ”という意味ではありません。向き合い方を知らないと入社後にギャップが生まれやすいという話なので、回避策も合わせて解説します。
| 視点 | よく言われる懸念 | 実際のところ / 回避策 |
|---|---|---|
| 技術スキルの広がり | 案件が既存システムの保守中心で、最新技術を触りづらい。 | ① 情報システム部門でも内製化を進めている会社を選ぶ ② 勉強会参加・個人開発で補う |
| 開発プロセスの経験 | 運用保守が主で、アジャイル4やCI5などの実践が積みづらい。 | 社内で小規模でもPoC3や内製プロジェクトを提案すると裁量を得られるケースもあります。 |
| キャリアパスの不透明さ | ジョブローテーションで情シスから外れる。または管理職寄りになり、技術スペシャリストとして伸びにくい。 | 技術と業務知識の両輪を武器にすれば、CIO補佐やDX推進室などへの道も拓けます。 |
| 市場価値の測りにくさ | 「自社システムに詳しい」ことに評価が偏り、転職時にアピールしにくい。 | 共通技術(クラウド・SaaS連携・セキュリティ)を意識的に担当し、職務経歴書でアピールできるようにします。 |
| 給与・待遇 | 同年代の開発会社や外資ITと比べ、ベースが低めになりがち。 | 近年はDX人材確保のため、IT専門職グレード10を設ける企業も増加。入社前に給与制度を確認しましょう。 |
これらの懸念点がある一方で、社内SEならではのプラス面も存在します。
社内SEならではの3つのプラス面
- 事業理解が深まる:システムとビジネス両方を把握し、経営層に直接提案できるポジションを目指せます。
- ワークライフバランスの安定:24時間運用監視を外部委託している場合、開発会社より休日などが安定しやすい傾向にあります。
- 調整力が鍛えられる:各部門と対話しながら要件を固めるため、PMやコンサルタント寄りのスキルが自然と身につきます。
【新卒のキャリア戦略】社内SEは本当に「やめとけ」?後悔しないための道筋
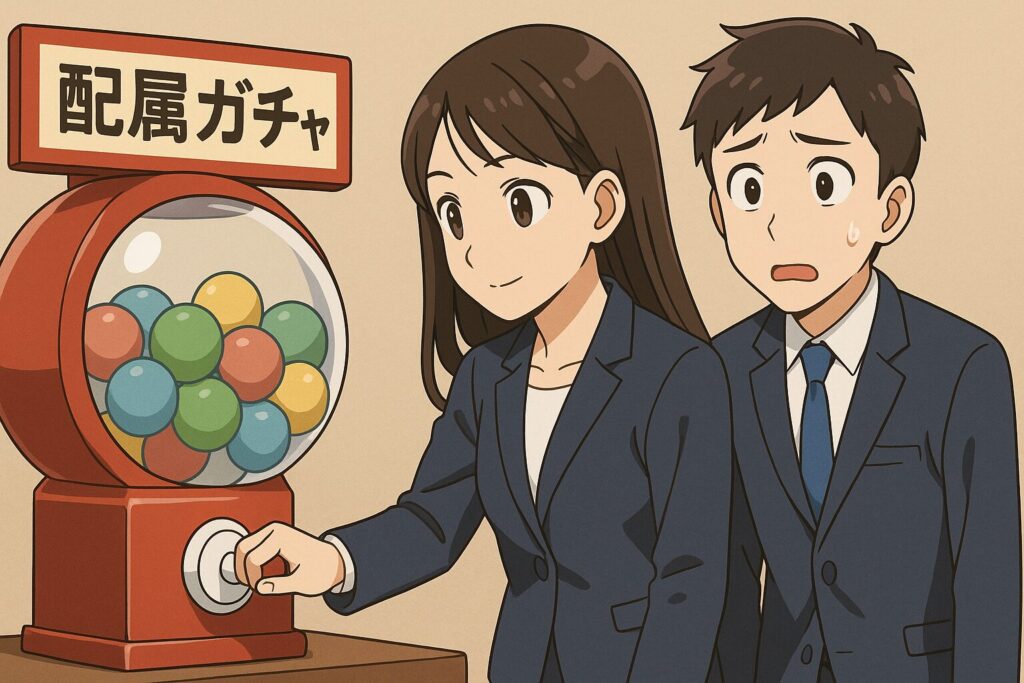
では、新卒で社内SEを目指す場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは、新卒の方が直面するリアルな課題と、それを乗り越えるための戦略を解説します。
新卒のリアル:「配属ガチャ」という最大の壁
新卒で社内SEを目指す際に、まず知っておくべき最も大きな現実。それが「配属ガチャ」です。これは、希望通りに情報システム部門に配属されない可能性があるという、多くの日本企業が抱える構造的な問題点を指します。
なぜこの問題が起きるかというと、多くの企業がIT部門専門ではなく「総合職」として新卒を一括採用するためです。そのため、社内SEになりたいと希望しても、最初の配属が営業や管理部門になるケースは珍しくありません。

ですから、新卒の場合は「社内SEになる」というより、「将来的に社内SEになれる可能性がある会社に入る」という視点がより正確です。
新卒向け:社内SEとのマッチ度診断
まず、あなたが社内SEという働き方に合っているか、自己分析してみましょう。キャリアの方向性を考える良い機会になります。
こんなタイプなら社内SEにマッチしやすい
- 技術そのものより「ITで業務を変える」ことに興味がある
- 腰を据えて一社の業務を極めたい
- 将来的にPMやIT企画、DX推進に進みたい
逆に、「フルスタック6でコードを書き続けたい」「最新技術を追いかけること自体がモチベーション」という方は、Web系企業や開発会社のほうが成長を実感しやすいでしょう。
新卒が取るべきアクション:次の一歩を決める3つのヒント
配属リスクがあるからこそ、新卒の企業選びは非常に重要です。「どの部署に配属されても、ITへの理解が深く、将来的に情報システム部門で活躍できるチャンスがある会社」を選びましょう。以下のヒントを参考に、企業の本質を見抜いてください。
新卒向け:企業を見抜く3つのヒント
- OB・OG訪問やカジュアル面談を活用する:実際の業務割合(開発 vs. ベンダー管理)や、若手のキャリアパスを確認しましょう。
- 評価制度と育成体制を調べる:評価制度に「技術専門職」グレードがあるか。また社内勉強会や技術ブログの有無は、IT人材を大切にする姿勢の表れです。
- IT戦略をチェックする:中期経営計画などで、内製開発比率やクラウド移行計画など、中長期のIT戦略が公開されているか確認しましょう。
【第二新卒のキャリア戦略】今がチャンス!社内SE転職を成功させる完全ガイド
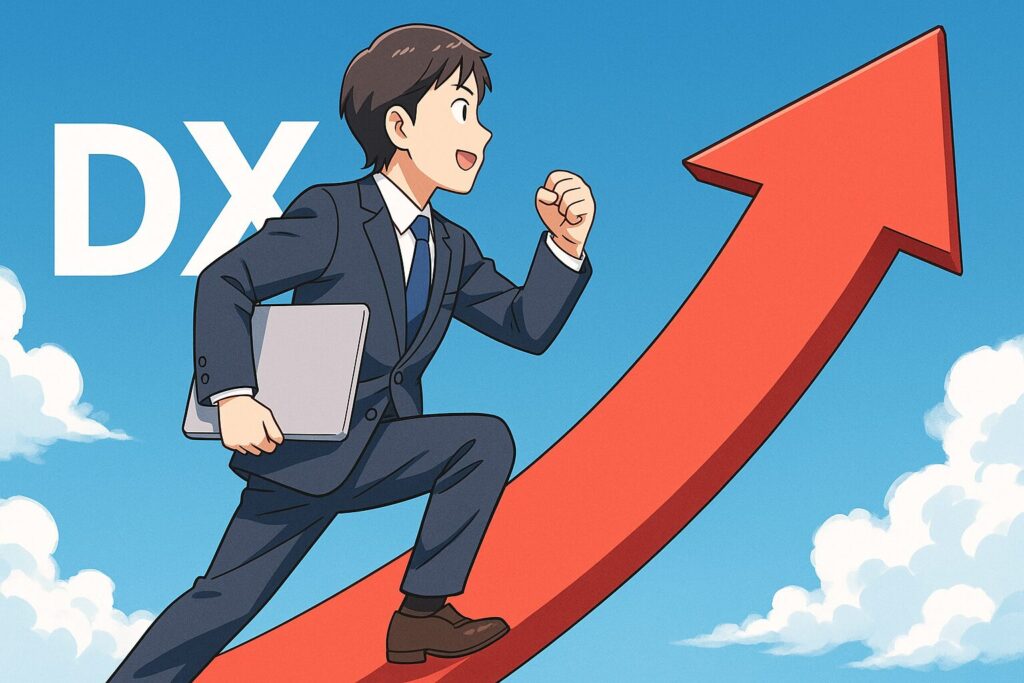
新卒とは対照的に、第二新卒にとって社内SEは非常に魅力的なキャリアチェンジの選択肢となります。その理由と具体的な戦略を、データと共にお伝えします。
データで見る市況:なぜ今がチャンスなのか?
まず、客観的なデータから現在の市況を見ていきましょう。なぜ「チャンス」と言えるのか、その根拠がここにあります。
| 指標 | 調査結果 |
|---|---|
| DX人材の不足感 | DXを推進する人材の量が「大幅に不足」と回答した日本企業は半数以上にのぼる。[1] |
| ITエンジニアの有効求人倍率 | 10倍を超える高い水準で推移しており、深刻な人手不足を示している。[2] |
【出典一覧】
- [1] IPA(独立行政法人情報処理推進機構)「DX白書2023」
- [2] パーソルキャリア株式会社「doda 転職求人倍率レポート」

第二新卒が社内SEに転じるメリットと注意点
このチャンスを最大限に活かすため、第二新卒ならではのメリットと、見落としがちな注意点を正直にお伝えします。冷静に比較検討することが、後悔しない選択につながります。
| メリット | 注意すべき落とし穴 |
|---|---|
| ① ビジネスと二人三脚で成長できる DX投資が膨らむ今、自動化やAI活用の提案でも主役を張れます。 |
① 人気職種ならではの狭き門 “人を増やしたい理由”が明確な会社(クラウド移行フェーズなど)を狙いましょう。 |
| ② プライベートを大切にしやすい 残業月10h以下や土日固定休の求人が増えています。 |
② 「古いシステムの番人」で終わるリスク 面談で「社内開発率」「CI導入状況」「クラウド比率」を具体的に確認します。 |
| ③ “手に職”と“業務知識”を両立できる 社内PMやIT企画、DX推進室へとステップアップを描きやすいです。 |
③ 技術を磨いても給料が上がりにくいリスク IT専門職グレードやジョブ型等級の有無は要チェックです。 |
| ④ SIerでの経験がそのまま武器になる コードや設計書の読解力があれば、技術面で貢献できます。 |
④ 器用貧乏で「武器」ができないリスク 自分の“主戦場”を決め、資格や社外勉強会で補強しましょう。 |
転職を成功させる5つのアクションプラン
メリットを最大化し、落とし穴を避けるための具体的な動き方を紹介します。この5つのステップを踏むことで、転職活動の成功率が大きく向上します。
第二新卒向け:成功への5つのアクション
まとめ:「職種」ではなく「自分に合った企業と役割」を選ぼう
今回は、新卒・第二新卒が社内SEを目指す上でのリアルな情報と、後悔しないための戦略を解説しました。
- 「やめとけ」の真相:5つの懸念点がありますが、それぞれに明確な回避策が存在します。
- 新卒の戦略:「配属ガチャ」を前提に、ITに本気な企業を見極めることが最重要です。
- 第二新卒の戦略:ポテンシャル採用のチャンスを活かし、メリットとデメリットを理解した上で具体的なアクションを起こしましょう。
- 成功の鍵:「社内SE」という職種名だけでなく、その企業がITにどのような「使命」を与えているかを見抜く「眼力」を養うことです。
あなたのキャリアプランと照らし合わせ、最適な一社を見つけてください。
FAQ:「新卒・第二新卒の社内SE」についてよくある質問
Q1. 結局、新卒ではSIerと社内SE、どちらが良いですか?
どちらが良いとは一概に言えません。「技術の基礎を徹底的に固めたい」と考えるなら、まずはSIerで数年間、開発経験を積むのが王道と言えるでしょう。
そこで実践的な開発スキルと顧客折衝能力を身につけてから事業会社の社内SEに転職すれば、より市場価値の高いエンジニアになれます。

Q2. もし希望しない部署に配属(配属ガチャ)されたらどうすれば?
まずは、配属された部署で3年間、全力で成果を出すことを目指しましょう。そこで実績を上げ、信頼を得ることが、将来的に情報システム部門へ異動希望を出す際の最も強力な交渉材料になります。

Q3. 企業のサイトを見るだけで、DXに本気かどうかを見分けるコツはありますか?
はい、いくつかポイントがあります。企業のトップメッセージやIR情報(株主向け情報)に、「DX」や「IT戦略」といった言葉が頻繁に出てくるかを確認しましょう。
また、採用ページにIT部門の社員インタビューが充実していたり、技術ブログを運営していたりする企業は、IT人材の育成や情報発信に積極的である可能性が高いです。
Q4. 第二新卒の面接では、新卒の時と何が一番違いますか?
「なぜ前の会社を辞めたのか」という転職理由と、「なぜこの会社で社内SEなのか」という志望動機の一貫性が、最も厳しく見られます。新卒のようにポテンシャルだけでは評価されません。
「前職では〇〇という経験を積んだが、△△という目標を達成するために、貴社の社内SEとして□□に貢献したい」という、過去・現在・未来を繋ぐストーリーを語れるかどうかが重要です。
Q5. 文系出身でも、新卒・第二新卒から社内SEになれますか?
はい、可能です。ただし、ITの基礎知識を学ぶ努力は不可欠です。ITパスポートや基本情報技術者試験7といった資格を取得することで、ITへの学習意欲と適性を客観的に示せます。
特に社内SEは、技術力だけでなく、他部署との調整能力といったコミュニケーション能力も非常に重視されます。そのため、文系出身者の強みを活かせる場面はたくさんあります。
この記事で使われている専門用語の解説
- 1. レガシーシステム
- 「時代遅れの遺産」といった意味で、長年使われ続けている古い技術や設計思想で構築された基幹システムのこと。維持・保守はできますが、新しいビジネス環境への対応が難しいことが多いです。
- 2. コストセンター
- 企業の部門のうち、売上や利益に直接貢献するのではなく、経費(コスト)として管理される部門のことです。対義語は、売上を生み出す営業部門などの「プロフィットセンター」です。
- 3. PoC (Proof of Concept)
- 「概念実証」の略。新しいアイデアや技術が、実現可能か、また期待する効果が得られるかを確認するための、小規模な検証プロジェクトのことです。
- 4. アジャイル
- 短いサイクルで「計画→設計→開発→テスト」を繰り返す開発手法です。変化に強く、スピーディーな開発が可能です。
- 5. CI (Continuous Integration)
- 「継続的インテグレーション」の略。開発者が書いたコードを自動でテスト・統合する仕組みで、アジャイル開発を支える重要な技術です。
- 6. フルスタックエンジニア
- Web開発におけるフロントエンド(見た目部分)からバックエンド(裏側の処理)、インフラまで、幅広い技術領域を一人で担当できるスキルを持つエンジニアを指します。
- 7. 基本情報技術者試験
- ITの基礎知識を証明する国家資格。「基本情報」や「FE」と略されます。
- 8. AWS SAA
- 「AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト」の略。Amazonのクラウドサービスに関する代表的な認定資格です。
- 9. AZ-104
- 「Microsoft Certified: Azure Administrator Associate」の試験番号。Microsoftのクラウドサービスに関する代表的な認定資格です。
- 10. IT専門職グレード / ジョブ型等級
- 会社の給与制度の一種です。IT専門職グレードは、エンジニアの技術力を評価して給与を決める特別な等級制度。ジョブ型等級は、年功序列ではなく、その人が担う職務(ジョブ)の重要度や難易度に応じて給与を決める制度を指します。
- 11. オンプレAD / Azure AD
- ADはActive Directoryの略で、組織内のユーザーIDやPCを一元管理する仕組みです。オンプレADは自社サーバー上で、Azure ADはMicrosoftのクラウド上で管理するサービスを指します。