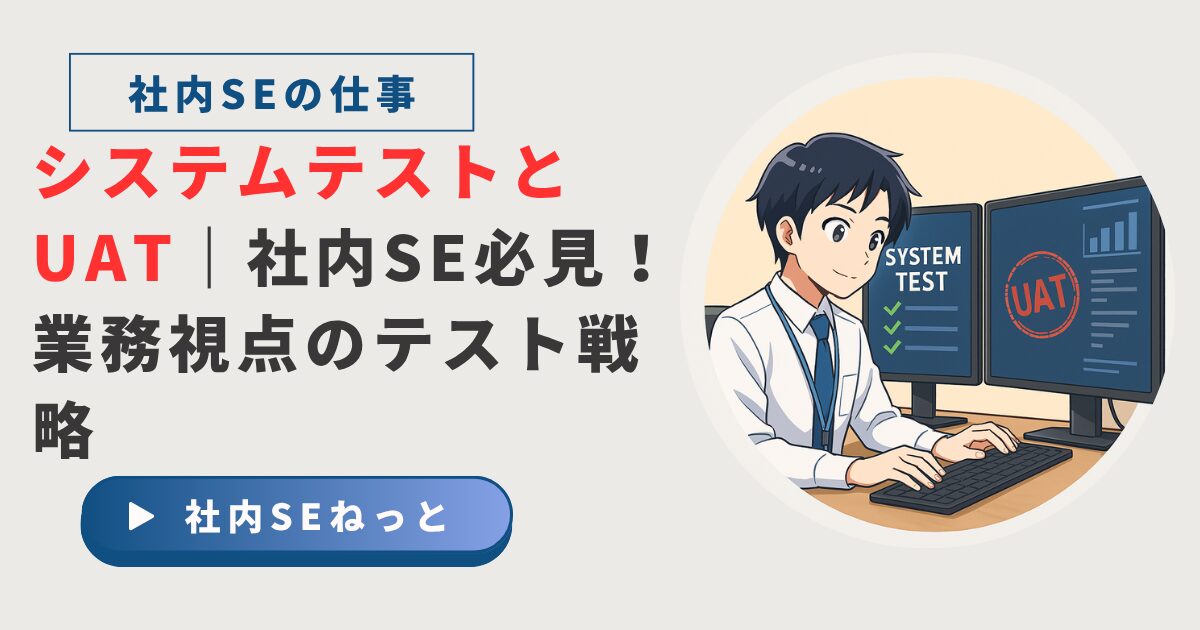「開発会社に任せきりで大丈夫?UATで業務部門をどう巻き込めばいいんだろう…」
「今の会社のテストの進め方、もっと良くできないかな?他社の事例も知りたい…」

システム開発プロジェクトの終盤に待ち受ける「テスト工程」。特にSIerやSESで開発に携わってきた方にとっては馴染み深い言葉ですが、社内SEの立場で関わるテストは、その目的も役割も大きく異なります。
結論から言うと、社内SEはテスト工程において、技術的な仕様を確認する「監督役」と、ビジネス価値を最終検証する「ファシリテーター」という2つの重要な役割を担います。特に後者のユーザー受け入れテスト(UAT)では、プロジェクトの成否を握る非常に重要な立ち回りが求められます。
この記事では、システムテストとUATにおける社内SEの役割の違いから、UATを成功に導くための具体的な実践マニュアルまで、私の経験を交えながら徹底的に解説します。
この記事を読めば、こんなことが分かります!
- 「システムテスト」と「UAT」における社内SEの役割の明確な違い
- UATを成功に導くための計画からリリース判断までの4つのステップ
- 多忙な業務部門からUATへの協力を引き出すための具体的な「巻き込み術」
- SIerのSEと社内SEの、テストに対する根本的なマインドセットの違い
この記事は「システム開発」の最終工程である「テスト」フェーズに特化した詳細記事です。開発全体の流れや、担当業務の全体像を掴みたい方は、以下の記事からご覧ください。
>>業務システム担当の仕事内容 全体像ガイド
システムテスト|社内SEはベンダーの「監督役」に徹する
UATの話に入る前に、その前段であるシステムテストについて触れておきます。
システムテストとは、開発されたシステム全体が、要件定義書や設計書に定められた機能・性能を仕様通り満たしているかを検証するテストです。一般的に、このテストの実行主体は開発ベンダーとなります。
ここでの社内SEの役割は、自らテストを行う「実行者」ではなく、開発ベンダーのテストが計画通り、かつ十分な品質で行われているかを監督・レビューする「監督役」です。
- テスト計画・ケースのレビュー:ベンダーが作成したテスト計画書やテストケースに、重要な観点の漏れがないか、第三者の視点でレビューします。
- テスト結果の評価:ベンダーから提出されるテスト結果報告書を確認し、品質が要求水準に達しているかを評価します。
- 進捗のモニタリング:テストが計画通りに進んでいるかを監視し、問題があれば早期に対応を促します。
このシステムテストで技術的な品質を担保した上で、いよいよプロジェクト最大の山場であるUATへと進みます。
UAT|事業視点でシステムの「妥当性」を問う最終検証
ユーザー受け入れテスト(UAT)1は、システムが本番稼働する前の最終検証プロセスです。
システムテストが「仕様書通りに作られているか」を検証するのに対し、UATは「このシステムで、我々の業務は本当に遂行できるか」を検証する場です。たとえ仕様書通りでも、実際の業務で使えなければ意味がありません。


【UAT実践マニュアル】計画からリリース判断までの4ステップ
それでは、社内SEがUATをどのように主導していくのか、具体的な進め方を4つのステップで解説します。
STEP1:計画フェーズ「目的とゴールを定める」
UATの成否は、この計画フェーズで8割決まると言っても過言ではありません。社内SEは「計画者」として、業務部門と協力し、UAT計画書を策定します。
- 目的と範囲の明確化:何を確認するためにUATを行うのか、どの業務プロセスを対象とするのかを定義します。
- 体制と役割分担の定義:誰がテストし、誰が評価し、誰が不具合を管理するのか、関係者の役割を明確にします。
- スケジュールの策定:テスト期間、不具合修正期間、再テスト期間などを具体的に計画します。
- 合否判定基準の設定:どのような状態になれば「合格(リリースOK)」とするのか、明確な基準を事前に全員で合意しておきます。
STEP2:準備フェーズ「現場のリアルな業務シナリオを作る」
UATの価値は、テストシナリオの質で決まります。社内SEは、ユーザーが質の高いシナリオを作れるよう、ファシリテーターとして支援します。
- 業務フローをベースにする:実際の業務の流れに沿ってシナリオを作成するよう促します。
- 例外ケースを洗い出す:問題なく処理が進むケース(ハッピーパス)だけでなく、「急なキャンセル処理」「月末の締め処理でのエラー」といった、ビジネスに直結する例外シナリオを洗い出すことが極めて重要です。
- テスト環境・データを準備する:本番に近いテスト環境と、リアルなテストデータをベンダーやインフラ担当と協力して準備します。


STEP3:実行フェーズ「ユーザーとベンダーの『橋渡し役』に徹する」
テスト期間中、社内SEはプロジェクトの円滑な進行を支える「調整役」に徹します。
- ユーザーサポート:テスターからの操作に関する質問に答えたり、問い合わせ窓口として機能したりします。
- 課題の一次切り分け:ユーザーからの報告が「システムの不具合」なのか「仕様の認識違い」なのか「単なる操作ミス」なのかを切り分け、開発ベンダーへ正確に伝えます。
- 進捗管理:テスト全体の進捗状況を常に把握し、遅れがあれば関係者にアラートを出し、対策を協議します。


STEP4:クロージングフェーズ「不具合を『仕分け』、リリースを判断する」
テストが完了したら、その結果を評価し、最終的なリリース判断を下します。ここでの社内SEの役割は、単なるまとめ役ではありません。
- 不具合の「仕分け(トリアージ)」:挙がってきた課題を、その重要度に応じて「リリース前に修正必須の致命的な欠陥」なのか、「リリース後の改善要望」なのかを判断(トリアージ2)します。
- ベンダーとの交渉:修正が必要な項目について、ベンダーと対応の優先順位やスケジュールを交渉します。
- リリース判定会議の主導:UATの結果と残存リスクを経営層や業務部門の責任者に報告し、「受け入れる(Accept)」かどうかの最終判断を促します。
UAT最大の壁!多忙なエース社員を巻き込む「仕組み作り」
UATの成否は、業務部門の主体的な参加にかかっています。しかし、多忙な業務部門から協力を得ることは、簡単ではありません。


このような状況を打開するには、会社全体を巻き込んだアプローチが不可欠です。
- 経営層のコミットメントを得る:最も効果的なのはトップダウンです。UATの重要性を経営層に理解してもらい、全社的な協力体制を指示してもらうことが成功への近道です。
- 負荷軽減策を提示する:テストツールを導入したり、テストに集中できる会議室を確保したり、データ準備を代行したりと、ユーザーの負担を少しでも軽くする工夫をします。
- 評価への反映を働きかける:UATへの貢献度を、部門や個人の業績評価に組み込んだり、プロジェクト期間中は本業と情シスを兼務扱いにしたり、といった会社の協力体制を引き出すのも重要な仕事です。
【補足】テストを効率化する新しい波|AI・自動化ツールの活用
近年、テスト業務を効率化するための新しい技術も登場しています。社内SEとして知っておきたい2つのトレンドをご紹介します。
- テスト自動化ツール:手動で行っていたテストケースの実行を自動化するツールです。特に、修正による影響がないかを確認する回帰テスト(リグレッションテスト)の効率化に絶大な効果を発揮します。SeleniumやPlaywrightといったツールが有名です。
- AIの活用:AIを活用して、テストケースを自動で生成したり、テスト結果を分析して不具合の原因を推測したりするサービスも登場しています。これにより、テスト設計や不具合解析の工数を大幅に削減できる可能性があります。
これらのツールは、導入や運用に専門知識が必要ですが、テストの品質とスピードを飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めています。
まとめ:UATは社内SEの価値が最も輝く舞台
ここまで、システムテストとUATにおける社内SEの役割、そしてUATを成功に導くための具体的なステップを解説してきました。
テスト工程、特にUATは、単なる品質保証活動ではありません。それは、社内SEが「事業の当事者」として、技術と業務の間に立ち、ビジネス価値を最大化するプロセスそのものです。
責任は重く、調整は大変ですが、それを乗り越えてプロジェクトを成功に導いた時の達成感は、何物にも代えがたいやりがいとなります。
社内SEへの転職やキャリアアップを考え始めたあなたへ
社内SEというキャリアに興味が湧いたら、次はいよいよ具体的な転職活動の準備です。でも、「何から始めればいいの?」「自分に合う転職エージェントは?」と迷ってしまいますよね。
そんなあなたのために、転職の成功確率をグッと上げるための記事を2つご用意しました。ご自身の状況に合わせて、ぜひご覧ください。
FAQ:「システムテスト」「UAT」についてよくある質問
Q1. システムテストとUATの主な違いは何ですか?
A1. 一番の違いは「目的」と「主体」です。システムテストは「仕様書通りか」を「開発側」が検証するのに対し、UATは「業務で使えるか」を「利用者側」が検証します。
Q2. UATの主体は業務部門とのことですが、社内SEは何をするのですか?
A2. 社内SEは、UATが円滑かつ効果的に進むよう、全体を計画・推進する「ファシリテーター」の役割を担います。計画立案、環境準備、ユーザー支援、ベンダーとの連携など、その業務は多岐にわたります。
Q3. テストケースはどこまで細かく作るべきですか?
A3. ケースバイケースですが、重要なのは網羅性です。特に、業務上の重要度やリスクが高い機能については、実際の業務シナリオに沿って、正常系だけでなく例外系も含めて具体的に記述することが望ましいです。
Q4. 社内SEとしてテスト業務に関わることは、キャリアアップに繋がりますか?
A4. はい、非常に繋がります。UATの推進を通じて、システム全体の理解、業務知識、プロジェクト管理能力、交渉力など、より上流のポジションに不可欠なスキルが総合的に磨かれます。
用語解説
- 1. UAT (User Acceptance Test)
- ユーザー受け入れテスト。開発されたシステムが、実際の業務で問題なく利用できるかを、システムを利用するユーザー自身が主体となって確認する最終テスト工程のこと。
- 2. トリアージ (Triage)
- 元々は医療現場で使われる言葉で、患者の重症度に応じて治療の優先順位を決めること。システム開発の文脈では、報告された不具合や課題の重要度・緊急性を評価し、対応の優先順位を決定することを指す。