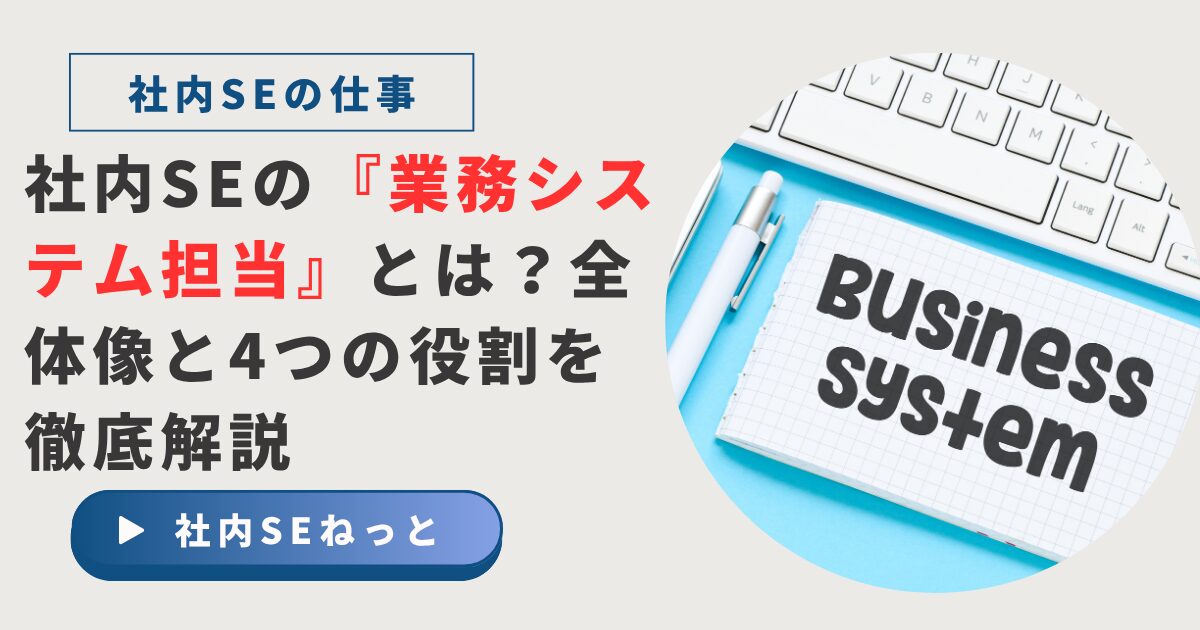「今のSIerでの開発経験は活かせるのかな? それとも全く違うスキルセットが必要?」
「ユーザーとベンダーの板挟みで大変って聞くけど、実際のところどうなの?」

SIerやSESからのキャリアチェンジを考えるとき、多くの疑問が浮かびますよね。
結論から言うと、社内SEの「業務システム担当」とは、単なる発注者や開発者ではなく、自社の事業を当事者としてITで動かす、やりがいの大きい専門職です。
その魅力と、SIerでの経験を活かしながらさらに成長するためのポイントはどこにあるのか。この記事では、業務システム担当の仕事の全体像から、具体的なキャリアパスまで、私の実体験を交えながら網羅的に解説します。
この記事を読むと、こんなことが分かります!
- 社内SE「業務システム担当」のミッションとSIerとの根本的な違い
- システム企画から開発、運用、改善までの一連の仕事の流れ(ライフサイクル)
- 「開発」「テスト」「運用」「プロジェクト管理」各フェーズでの具体的な役割
- 業務システム担当に本当に求められるスキルセット
- この仕事ならではのやりがい、大変さ、そしてキャリアの将来性
この記事では「業務システム担当」の仕事に絞って深掘りしますが、社内SEには他にも多様な職種があります。まずは社内SEの全体像を掴みたいという方は、こちらの完全ガイドからご覧ください。
>>【社内SE完全ガイド】仕事内容からキャリアパスまで、現役が本音で解説
SIerとは違う!社内SE「業務システム担当」のミッション
業務システム担当の最も重要なミッションは、「自社の事業を成功させるために、最適なシステムを企画・導入・改善し続けること」です。
これは、顧客の要望通りにシステムを納品することが目的であるSIerとは、立ち位置が根本的に異なります。システムはあくまで手段であり、目的は常に「自社の事業成長」。この視点の違いが、仕事の面白さであり、難しさでもあります。

業務システム担当の仕事ライフサイクル
業務システム担当の仕事は、一度作って終わりではありません。「企画」から「廃棄」まで、システムの一生に寄り添い続ける、壮大なライフサイクルで構成されています。
この全体像を理解することが、業務システム担当の役割を掴む第一歩です。

- 企画:経営戦略や現場の課題に基づき、「何のために、どんなシステムが必要か」を構想する。
- 開発・導入:構想を具体的な形にする。社内SEは主に要件定義やベンダーコントロールを担う。
- テスト/UAT:完成したシステムが業務で本当に使えるかをユーザー目線で検証する。
- 運用・保守:日々の安定稼働を支えながら、ユーザーからの声やデータを収集・分析する。
- 改善・廃棄:収集した情報を基に、さらなる改善を行ったり、役目を終えたシステムを終了させたりする。
このように、システムの一生すべてに関与し、常に「これは自社のビジネスに貢献しているか?」と問い続けるのが、業務システム担当の大きな特徴です。
以降の章で、特に重要な4つのフェーズについて、具体的な仕事内容とより詳細な解説記事へのリンクをご紹介します。
【フェーズ1】システム開発|「何を作るか」を事業視点で決める舵取り役
このフェーズでの業務システム担当の最も重要な役割は、プロジェクトの「舵取り役」です。SIerのように言われたものを作るのではなく、「事業のために本当に必要なものは何か」を考え、定義し、プロジェクトを成功へと導きます。
業務システム担当が自らコードを書くことは稀ですが、その分、上流工程での判断が極めて重要になります。
- システム企画・要件定義:「なぜこのシステムが必要か」「何を実現したいのか」を経営層や業務部門とすり合わせ、システムの骨格を定義します。ただ要望を聞くだけでなく、「その機能は本当に必要か」「もっと費用対効果の高い方法はないか」を問いかけるのが腕の見せ所です。
- ITベンダー選定:RFP(提案依頼書)を作成し、複数のベンダーから提案を受け、技術力・コスト・実績などを比較検討して最適なパートナーを選びます。
- 設計レビュー・進捗管理:ベンダーが作成した設計書が、要件を満たしているか、将来的な拡張性はあるかなどをレビューします。SIerでの経験が最も活きる場面の一つです。

もっと詳しく知りたい方へ
システム開発フェーズにおける、社内SEならではのベンダーコントロール術や要件定義の勘所については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【フェーズ2】システムテスト/UAT|ユーザーとベンダーを繋ぐ「品質」の最後の砦
UAT(ユーザー受入テスト)は、開発されたシステムが本当に「使える」ものになっているかを保証する、「品質」の最後の砦です。ここでの業務システム担当の役割は、開発ベンダーとユーザー部門の「橋渡し役」に他なりません。
技術者の論理とユーザーの業務実態、その両方を理解し、プロジェクトをゴールに導く調整力が試されます。
- テスト計画の策定:どのような観点で、誰が、いつまでにテストを行うかを計画します。「ハッピーパス(正常系)だけではなく、イレギュラーな操作をどこまで試すか」など、リスクとコストのバランスを取る判断力が求められます。
- テストシナリオの作成支援:業務部門の担当者が実際の業務をスムーズに試せるよう、具体的な操作手順や確認項目をまとめたシナリオ作りを支援します。
- 不具合の切り分けと管理:発生した不具合が「システムのバグ」なのか「仕様の認識違い」なのかを切り分け、ベンダーと修正の調整を行います。ここでの冷静な判断と調整力が、プロジェクトの成否を分けることも少なくありません。
もっと詳しく知りたい方へ
開発の最終関門である「システムテスト」と「UAT」の具体的な進め方や、社内SEならではの業務視点でのテスト戦略については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【フェーズ3】システム運用・保守|ビジネスを止めず、改善に繋げる「宝の山」
システムが稼働した後の運用・保守フェーズは、次のビジネス改善のヒントが眠る「宝の山」です。単にシステムを守る「守りのIT」だけでなく、ユーザーの声やシステムログから課題を見つけ出し、「攻めのIT」に繋げることが真価を発揮するポイントです。
日々の地道な業務の中に、会社の未来を変えるチャンスが隠されています。
- ユーザーからの問い合わせ対応:操作方法の質問から「もっとこうならないか」という改善要望まで、ユーザーの声を直接受け止めます。課題の本質を見極め、時には複数の部署にまたがる業務改善の起点となることもあります。
- 障害対応:システムトラブル発生時に、原因調査、暫定対応、恒久対応の指揮を執ります。ビジネスへの影響を最小限に抑えるための迅速な判断が求められます。
- システムの改善提案:問い合わせ内容や蓄積されたデータを分析し、「手作業で行っているこの業務を自動化できないか」など、業務効率化やコスト削減に繋がるシステムの改修を企画・提案します。
もっと詳しく知りたい方へ
システムの安定稼働を支える「守り」の業務と、そこから改善に繋げる「攻め」の視点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【全フェーズ共通】プロジェクト管理|SIerとは違う「事業の当事者」としての調整術
全てのフェーズを一貫して支えるのが、「事業の当事者」としてのプロジェクト管理能力です。SIerのPMが主にITベンダー側の進捗を管理するのに対し、業務システム担当は「自社(経営層、業務部門)」と「ITベンダー」の両方を調整する、より複雑な役割を担います。
利害関係が異なるステークホルダーの間に立ち、プロジェクトという船を目的地まで導く船長のような存在です。
- 進捗管理:プロジェクト全体のスケジュール、タスクの進捗を常に把握し、遅延があれば対策を講じます。
- 課題管理:発生した課題を記録し、関係者と解決策を協議し、クロージングまで追跡します。
- 予算管理:プロジェクトの予算と実績を管理し、超過しないようにコントロールします。
- ステークホルダー調整:立場や意見の異なる関係者(経営層、業務部門、ベンダーなど)の期待値を調整し、合意形成を主導します。
もっと詳しく知りたい方へ
SIerのPMとの違いや、事業会社の当事者としてプロジェクトを成功に導くための管理術については、こちらの記事で詳しく解説しています。
業務システム担当に必須の3つのスキルセット|技術力だけでは通用しない理由
業務システム担当として活躍するには、SIerで培った技術力だけでは不十分です。なぜなら、ミッションが「システムを作ること」ではなく、「ビジネスに貢献すること」だからです。
そのためには、技術、ビジネス、調整力という三位一体のスキルが不可欠になります。
技術スキル(テクニカルスキル)
特定の技術に深く精通していることよりも、広く浅くでも自社のシステム構成全般を理解し、技術の選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを理解して、ビジネス要件に最適なものを判断する能力がより重要になります。なぜなら、システム全体の最適化や、障害発生時の迅速な原因切り分けに繋がるからです。
ビジネススキル
これが最も重要なスキルかもしれません。自社の事業内容、業務フロー、そして業界の動向を深く理解する力です。現場の担当者が何に困っているのか、どうすれば業務が効率化するのかを肌で感じ取り、ITの言葉に翻訳して解決策を提示することが求められます。
調整力・交渉力(ソフトスキル)
業務部門、経営層、ITベンダーなど、立場の異なる人々の間に立ち、全員が納得するゴールへと導く力です。「板挟み」状態になることも日常茶飯事ですが、それを乗り越えてこそ頼られる存在になれます。相手の言うことをただ聞くだけでなく、時には代替案を示して交渉し、プロジェクトを前に進める粘り強さが不可欠です。
まとめ:事業の成長をITで支える、やりがいの大きい専門職
ここまで、社内SE「業務システム担当」の仕事について、その全体像を解説してきました。
SIerのような「作るプロ」とは異なり、自社の事業に深く入り込み、ビジネスの成長をITの力で直接的に支える。それが業務システム担当の最大の魅力です。
大変なことも多いですが、自分の仕事が会社の成長に直結しているという手応えは、何物にも代えがたいやりがいがあります。この記事が、あなたのキャリアを考える上での一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
社内SEへの転職やキャリアアップを考え始めたあなたへ
社内SEというキャリアに興味が湧いたら、次はいよいよ具体的な転職活動の準備です。でも、「何から始めればいいの?」「自分に合う転職エージェントは?」と迷ってしまいますよね。
そんなあなたのために、転職の成功確率をグッと上げるための記事を2つご用意しました。ご自身の状況に合わせて、ぜひご覧ください。
FAQ:「業務システム担当」についてよくある質問
Q1. 未経験から社内SEの業務システム担当になれますか?
A1. 完全にIT業界が未経験という状態からの転職は難しいですが、不可能ではありません。SIerでの開発・インフラ運用経験や、事業会社の情報システム部門でのヘルプデスク経験など、何らかのIT関連業務の経験があれば、そこから業務システム担当へのキャリアチェンジは十分に可能です。
Q2. プログラミングスキルは必須ですか?
A2. 必須ではないケースが多いです。業務システム担当は自らコードを書くことよりも、ベンダーが作成した設計書をレビューしたり、技術的な課題について対等に会話したりする能力の方が重視される傾向にあります。とはいえ、プログラミングの知識があれば、ベンダーとのコミュニケーションや見積もりの妥当性判断において大きな強みになります。
Q3. 業務システム担当に役立つ資格はありますか?
A3. 資格が必須な求人は稀ですが、知識と意欲の証明になります。「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者試験」はITの基礎知識の証明に役立ちます。キャリアアップを目指すなら、上流工程のスキルを示す「プロジェクトマネージャ試験(PM)」や「ITストラテジスト試験(ST)」などが評価されやすいです。
Q4. SIerと比べて年収は上がりますか?
A4. 企業の規模や業界、個人のスキルセットによるため一概には言えません。しかし、より上流の工程(企画、要件定義、予算管理など)を担い、自社の事業に直接貢献するポジションであるため、成果次第でSIer時代よりも高い評価と年収を得るチャンスは十分にあります。