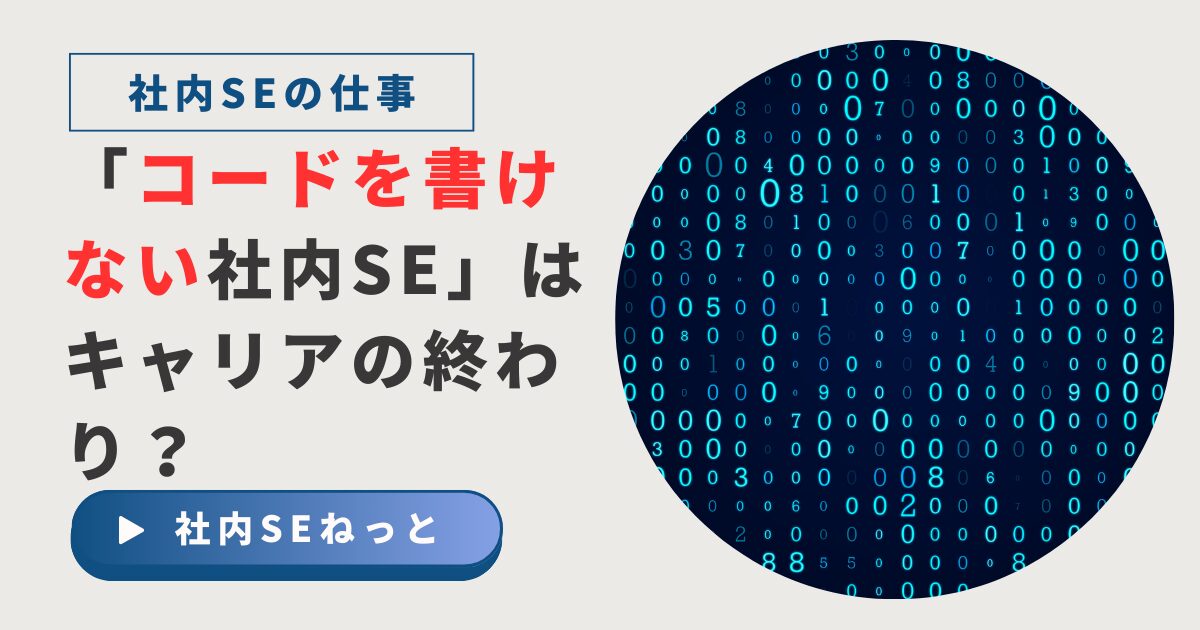「プログラミングできないエンジニアなんて、市場価値がないと思われそう…」
「このままで、俺のエンジニアとしてのキャリアは大丈夫なんだろうか?」

技術者としてキャリアを歩んできたあなたが、「コードを書けない」という状況に不安や焦りを感じるのは、至極当然のことです。

しかし、結論からお伝えします。「コードが書けない = 市場価値がない」という考えは、もはや過去の幻想です。むしろそれは、「ビジネスを語れるエンジニア」という、新しい市場価値を手に入れるためのスタートラインなのです。
この記事では、あなたのその不安を「武器」に変えるための、具体的なキャリア戦略を徹底的に解説します。
この記事を読めば、こんなことが分かります!
- 社内SEが「コードを書けない」と言われる本当の理由
- コードを書けなくても市場価値の高いエンジニアになるための「代替スキル」
- マネージャーやITコンサルなど、具体的なキャリアパスの選択肢
- それでも技術力を磨き続けたい場合の具体的なアクション
この記事は社内SEの「スキルセット」に特化した内容です。社内SEが抱えるネガティブな側面の全体像を知りたい方は、まずはこちらの親記事からご覧ください。
>>【社内SEはやめとけ】は本当?後悔する人の5つの特徴と失敗しない転職法
なぜ社内SEはコードを書く機会が減るのか?2つの構造的理由
まず、あなたの不安の根源である「なぜコードが書けなくなるのか」を正しく理解しましょう。これには、社内SEという職務の構造的な理由があります。
理由1:役割が「作る人」から「管理・調整する人」に変わるから
結論として、多くの会社で、社内SEの役割は「手を動かして作る人(プレイヤー)」ではなく、「プロジェクト全体を管理・調整する人(マネージャー)」へとシフトするからです。
なぜなら、システム開発を内製するよりも、専門の外部ベンダーに委託した方が、コストや品質、開発スピードの面で合理的だと判断する企業が多いからです。
その結果、社内SEの主な仕事は、ベンダーを選定し、社内からの要望を伝えて仕様を調整し、プロジェクトの進捗や予算を管理することになります。そうなると、自然と、コードに直接触れる時間は激減していくのです。
これは、役割の変化に伴う必然的な流れであり、あなたの能力とは関係ありません。
理由2:「ゼロから作る」より「既存を活かす」が求められるから
もう一つの理由は、社内SEのミッションが「ゼロから新しいものを作ること」よりも、「今あるものを最大限に活用して、ビジネス課題を解決すること」だからです。
近年は、SalesforceやMicrosoft 365といった高機能なSaaS1(クラウドサービス)が普及しています。ゼロからシステムを開発するよりも、これらの既存のサービスを導入し、自社の業務に合わせて設定・カスタマイズする方が、はるかに早く、安く課題を解決できます。
そのため、大規模なプログラミングよりも、製品知識や設定ノウハウ、そして「どのSaaSが自社の課題解決に最適か」を見極める選定能力が重視される場面が増えています。
このように、求められるスキルの中心が、コーディングからSaaSの活用へと移っているのです。
「コードが書けない」を武器に変える!市場価値の高い5つの代替スキル
コーディングスキルが錆びつく代わりに、あなたはSIer時代には得られなかった、より市場価値の高い「代替スキル」を身につけるチャンスを手にします。これこそが、社内SEのキャリアの醍醐味です。



スキル1:ビジネスを語る力(業務知識・業界知識)
結論として、社内SEの最も重要な価値は、自社のビジネスを深く理解し、「ITでどう儲けるか」「ITでどう効率化するか」を語れることです。
なぜなら、技術はあくまでビジネス課題を解決するための「手段」だからです。企業のDX2(デジタルトランスフォーメーション)を推進するには、この業務理解が不可欠です。
例えば、ユーザーの要望を鵜呑みにせず、「なぜこの機能が必要なのか」「本当の課題は何か」を突き詰め、ビジネスの根幹に影響を与える提案ができる。コーディングの専門家ももちろん重要ですが、社内SEのフィールドでは、技術とビジネスの両輪で物事を考えられる人材が、特に高く評価されます。
このスキルこそが、あなたの市場価値を大きく左右するのです。

スキル2:要件定義・要求具現化スキル - "翻訳家"としての価値
ITに詳しくないユーザーの「こんなことできたら良いな」という曖昧な想いを、ベンダーが開発できる具体的な「仕様」に落とし込む。この"翻訳家"としてのスキルは、極めて価値が高いです。
その理由は、プロジェクトの失敗のほとんどは、この最初のボタンの掛け違い、つまり要件定義3の失敗から生まれるからです。
ただ言われたことを右から左に流すのではなく、ユーザーの真のニーズを引き出し、具体的な形にして合意形成する。この能力は、プロジェクトを成功に導くための、まさに要となるスキルです。
このスキルを磨くことで、あなたはプロジェクトに不可欠な存在となれるでしょう。
スキル3:プロジェクトマネジメントスキル - "船長"としての価値
予算、品質、納期、そしてメンバーのモチベーションに責任を持ち、プロジェクトという船を目的地まで導く"船長"の役割です。
これは、単なるタスク管理ではありません。予期せぬトラブルに対応し、様々なステークホルダー4と交渉し、チームを鼓舞する。多くのエンジニアが「管理される側」であるのに対し、プロジェクト全体を俯瞰し、ビジネスの意思決定に関わるマネジメント経験は、あなたのキャリアを大きく飛躍させます。
この経験は、より高いポジションを目指す上で、非常に価値のあるスキルと言えます。
スキル4:ベンダーマネジメントスキル - "目利き"としての価値
複数のITベンダーの中から最適なパートナーを選び、彼らの見積もりや成果物が妥当であるかを正しく評価する。この"目利き"としての能力も、社内SEの重要な価値です。
なぜなら、ITに詳しくない経営層や他部署に代わって、プロの視点でベンダーをコントロールし、自社の利益を守る役割を担うからです。
コストを最適化し、品質を担保し、プロジェクトを円滑に進める。この役割を担える人材は、多くの企業で重宝されます。

スキル5:コミュニケーション・調整能力 - "潤滑油"としての価値
結論として、AIには決して真似のできない、人間ならではの高度なスキルが、この調整能力です。
その理由は、仕事は人と人との間で進むからです。経営層から現場の担当者、外部のベンダーまで、立場の違う人々の間に立ち、利害を調整し、物事を円滑に進める。
技術力だけでは解決できない社内の力関係や、複雑な人間関係を乗り越えてプロジェクトを成功に導く。この「人間力」とも言える調整能力は、経験を積んだ社内SEだからこそ発揮できる、非常に稀少な能力なのです。
コードを書かなくても高みを目指せる!4つのキャリアパス
これらの代替スキルを身につけたあなたには、コーディング中心のキャリアとは全く異なる、魅力的な道が拓けます。ここでは代表的な4つのキャリアパスをご紹介します。
キャリアパス1:チームを率いる「マネージャー職」
結論として、チームやプロジェクト全体を率いるマネージャー職は、社内SEが目指せる王道のキャリアパスの一つです。
なぜなら、多くの企業では、個別の技術力以上に、プロジェクト全体を俯瞰し、ビジネスの成功に責任を持つマネジメント能力が、より重要な役割として高く評価される傾向にあるからです。
具体的には、プロジェクトマネージャー(PM)として予算や進捗を管理したり、ITマネージャーとして部門全体の戦略やメンバーの育成を担ったりします。
このように、プレイヤーからマネージャーへと視座を高めることで、より大きなやりがいと責任ある立場で活躍できる道が拓けます。
キャリアパス2:経営の課題を解決する「ITコンサルタント」
社内SEとして培った知見を活かし、企業の経営課題をITで解決するコンサルタントとして活躍する道も、非常に有望です。
その理由は、あなたの持つ「事業会社の内部を知っている」という経験が、外部のコンサルタントにはない独自の強みになるからです。
例えば、IT戦略の立案やシステム導入を、より現場の実態に即した形で支援することができます。コードを書くことはほぼなく、論理的思考力と提案力が勝負の世界です。
客観的な立場で、より多くの企業の変革に関わることができる、やりがいの大きなキャリアです。
キャリアパス3:企業の変革を担う「DX推進の専門家」
特定の企業に深くコミットし、その会社のビジネスをITで直接変革するスペシャリストも、これからの時代にますます需要が高まるキャリアです。
なぜなら、今やあらゆる企業にとって、DXの推進は競争力を維持するための最重要課題だからです。
具体的には、AIやデータ活用といった最新技術の導入を企画・推進したり、社内の業務プロセスを根本から見直したりします。まさに会社の未来を作る、花形とも言える役割です。
自らの手で会社が変わっていく様子をダイレクトに実感できる、非常に魅力的な仕事と言えるでしょう。
キャリアパス4:自由な働き方を実現する「フリーランス・副業」
結論として、企業に所属せず、プロジェクト単位で専門性を発揮する自由な働き方も、十分に選択肢に入ります。
その理由は、あなたが得た要件定義やプロジェクト管理といった上流工程5のスキルは、フリーランス市場でも高く評価されるからです。
いきなり独立するのが不安な場合は、まず「業務自動化」や「IT導入支援」といったテーマで副業から始めてみるのも良いでしょう。
本業で安定を確保しつつ、社外で自分のスキルを試せる、リスクの低い始め方です。
それでも「コードを書き続けたい」あなたが採るべき3つの選択肢
もちろん、技術の探求こそがエンジニアの喜びだと考える方もいるでしょう。その情熱を諦める必要はありません。社内SEとして技術力を維持・向上させるための具体的な方法をお伝えします。

選択肢1:社内で「内製化」の旗を振る
最も挑戦的で、大きなリターンが期待できるのが、社内に開発文化を根付かせることです。
なぜなら、成功すれば、あなたは単なるエンジニアではなく、会社の歴史を変えた変革者として、非常に高い評価を得られるからです。
「外部委託ばかりでは、コストもかかるし、スピード感も遅い。これからは社内で開発部隊を作るべきだ!」と経営層に粘り強く提案し、自らがその中心メンバーとなるのです。
簡単な道ではありませんが、会社の文化を創り上げるという、何物にも代えがたい経験が得られるでしょう。
選択肢2:副業や個人開発で腕を磨き続ける
本業で得られない機会は、本業以外で補う、という考え方も非常に有効です。
その理由は、今の時代、スキルを磨く場所は会社の中だけに限られていないからです。
例えば、副業でWebサイト制作の案件を受けたり、自分の好きなサービスを個人開発したりすることで、技術のキャッチアップと実践経験の両方を手に入れることができます。
本業で安定した収入を得ながら、プライベートな時間で好きな技術を追求する。このバランスの取れた働き方も、一つの理想形です。
選択肢3:「内製化に強い企業」へ転職する
結論として、自分の志向と会社の文化をマッチさせることが、最も確実で効果的な方法です。
なぜなら、全ての社内SEがコードを書かないわけではなく、企業によっては積極的に自社開発(内製化6)を進めているところも存在するからです。
転職活動の際に、「内製化の比率」や「開発チームの体制」「使っている技術スタック」などをウェブサイトや面接でしっかりと確認しましょう。
自分の志向に合った文化を持つ企業を戦略的に選ぶこと。これが、後悔しないキャリア選択の鍵となります。
まとめ:「書けない」は弱みではない。「語れる」が武器になる時代へ
「コードが書けない」という不安について、その原因と具体的なキャリア戦略を解説してきました。
- 「書けない」理由:社内SEの役割が「プレイヤー」から「マネージャー」「調整役」に変わるため。
- 代替スキル:コーディングの代わりに、業務知識、要件定義、マネジメントといった、より上流のスキルが身につく。
- キャリアパス:身につけたスキルを活かし、管理職やITコンサルタントなど、コーディングに依存しない多様なキャリアが拓ける。
- 結論:これからの時代は、単にコードが書けるだけでなく、ビジネスの課題をITで解決できる人材の価値がますます高まる。
あなたの「コードが書けない」という悩みは、決してキャリアの終わりではありません。それは、技術とビジネスの両方を理解する、市場価値の高いエンジニアへと進化するための、始まりの合図なのです。その事実に自信を持ち、新たなキャリアへと踏み出してください。
自分の市場価値を正しく知り、キャリアの可能性を広げたいあなたへ
「コードを書かない自分のキャリアに、どんな選択肢があるんだろう?」「自分のスキルは、他の会社でどれくらい評価されるんだろう?」――そんな疑問を持ったら、転職エージェントに相談するのが一番の近道です。
あなたの経験を客観的に評価し、あなたに合った多様なキャリアパスを提案してくれる、社内SEの転職に本当に強い転職エージェントだけを厳選して比較した記事をご用意しました。
>>【失敗しない】社内SE転職エージェント選び|おすすめ12社を比較
そもそも転職活動の進め方から不安な方は、こちらの記事で全体像を掴んでください。
FAQ:「コードが書けない」社内SEについてよくある質問
Q1. 本当にプログラミング未経験でも社内SEになれますか?
A1. はい、可能です。特に、インフラ管理やヘルプデスク、IT資産管理といった業務が中心の求人であれば、プログラミングスキルが問われないケースは多くあります。ただし、SIerなどでの何らかのIT実務経験は求められることがほとんどです。
Q2. 年収を上げるには、やはりコードが書けた方が有利ですか?
A2. 一概にそうとは言えません。プレイヤーとして高年収を目指すならコーディングスキルも武器になりますが、プロジェクトマネジメントやITコンサルティングといった上流工程のスキルの方が、より高い年収レンジを狙える傾向にあります。重要なのは「どのスキルで頂点を目指すか」という戦略です。
Q3. 技術的な話ができないと、ベンダーになめられませんか?
A3. 詳細な技術を理解している必要はありませんが、「この機能はなぜ必要なのか」「それがビジネスにどう貢献するのか」を論理的に説明できれば、ベンダーはあなたを軽視できません。技術の議論ではなく、ビジネスの議論で主導権を握ることが重要です。
Q4. スキルアップのために、どんな資格を取るのがおすすめですか?
A4. マネジメント志向なら「プロジェクトマネージャ試験」、IT戦略に関わりたいなら「ITストラテジスト試験」がおすすめです。また、クラウドが主流の現代では「AWS認定ソリューションアーキテクト」なども、インフラ寄りの知識を証明する上で非常に有効です。
Q5. 社内SEの面接で「どんな技術を伸ばしたいか」と聞かれたら、どう答えるべきですか?
A5. プログラミング言語の名前を挙げるだけでなく、「〇〇という業務課題を解決するために、△△というクラウドサービスの知識を深め、業務効率化に貢献したいです」といったように、「目的」とセットで答えるのが良いでしょう。技術の習得が自己目的化していない、ビジネス視点を持った人材であることをアピールできます。
この記事で使われている専門用語の解説
- 1. SaaS (サース)
- Software as a Serviceの略。利用者がソフトウェアを自身のコンピュータにインストールするのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態。Microsoft 365やSalesforceなどが代表例。
- 2. DX (デジタルトランスフォーメーション)
- デジタル技術を活用して、企業のビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などを根本的に変革し、競争上の優位性を確立すること。単なるIT化ではなく、変革を目的とする。
- 3. 要件定義 (ようけんていぎ)
- システム開発において、実装すべき機能や満たすべき性能などを明確にする作業のこと。プロジェクトの成功を左右する最も重要な工程の一つ。
- 4. ステークホルダー
- プロジェクトや企業の活動における「利害関係者」のこと。顧客、株主、経営者、従業員、取引先など、その活動に影響を与えたり、影響を受けたりする全ての人々を指す。
- 5. 上流工程 (じょうりゅうこうてい)
- システム開発における初期段階の工程のこと。一般的に、企画、要件定義、基本設計などを指す。下流工程(詳細設計、プログラミング、テスト)の土台となる。
- 6. 内製化 (ないせいか)
- これまで外部の業者に委託していた業務を、自社の組織や人員で行うように切り替えること。システム開発においては、外部ベンダーに頼らず自社で開発することを指す。