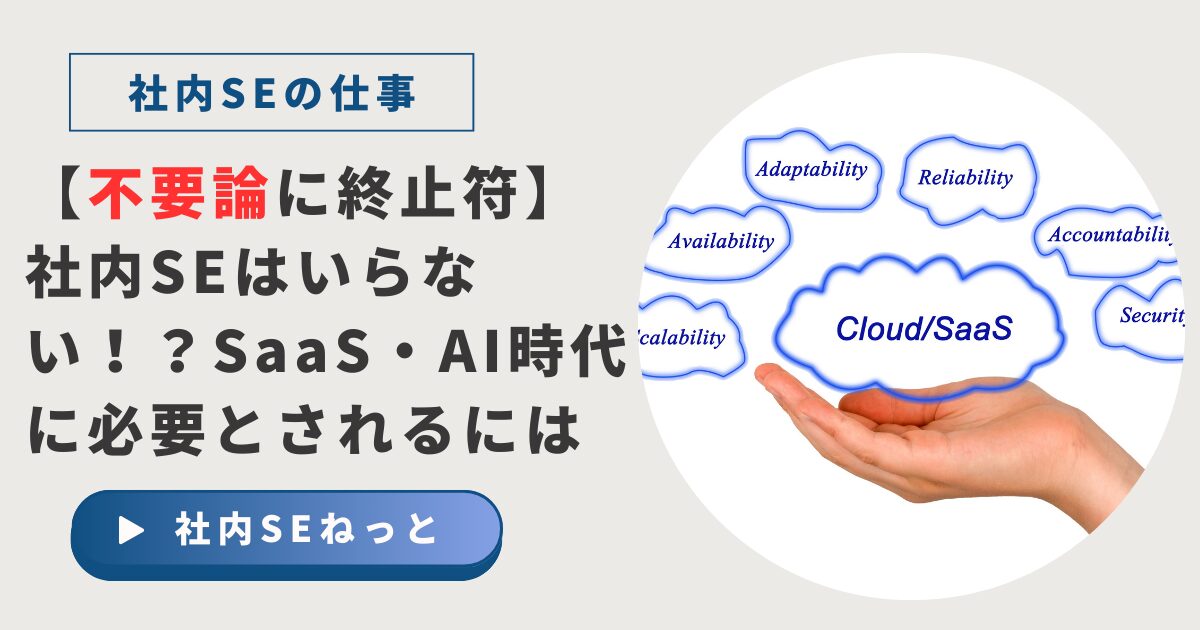SaaSやAIの目覚ましい進化を目の当たりにして、「今の自分の仕事は、いつかなくなってしまうのではないか…」と、漠然とした不安を抱くのは、あなただけではありません。
結論からお伝えします。旧来の「システムの守り番」としての社内SEは、確かにもういらないかもしれません。しかし、それは「企業の変革をリードする戦略的ITパートナー」という、新たな主役の登場を意味しているのです。
この記事では、「社内SE不要論」の真相を解き明かし、これからの時代にあなたの市場価値を爆発的に高めるための、具体的なキャリア戦略を解説します。
この記事を読めば、こんなことが分かります!
- 「社内SEはいらない」と言われる本当の理由
- 淘汰される人材と、逆にAI時代に価値が爆上がりする人材の違い
- これからの社内SEに求められる3つの必須条件
- 未来を生き抜くための具体的なキャリア戦略
この記事は社内SEの「将来性」に特化した内容です。社内SEが抱えるネガティブな側面の全体像を知りたい方は、まずはこちらの親記事からご覧ください。
>>【社内SEはやめとけ】は本当?後悔する人の5つの特徴と失敗しない転職法
なぜ「社内SEはいらない」と言われるのか?3つの大きな時代の波
まず、私たちが直面している現実を正しく理解しましょう。「社内SE不要論」は、単なる噂ではありません。それは、IT業界における3つの大きな時代の波によって引き起こされています。
波1:SaaSの普及 -「作る」から「使う」へ
結論として、高機能なSaaS1の登場により、自社でシステムを開発・保有する必要性が低下したことが、不要論の最大の要因です。
なぜなら、専門知識がなくても、各部署が簡単にツールを導入できるようになったため、従来の「システムの守り番」としての役割が求められなくなってきたからです。
例えば、SalesforceやGoogle Workspaceなどの導入で、サーバー管理やソフトウェアのインストールといった業務が不要になったケースは、枚挙にいとまがありません。
このように、誰でもITツールを使えるようになったことが、旧来の社内SEの存在意義を揺るがしているのです。
波2:AIによる自動化 -「人の手」から「機械の手」へ
AI2技術の進化が、社内SEの定型業務を代替し始めていることも、大きな要因です。
その理由は、これまで人手に頼っていた問い合わせ対応や単純な運用作業が、AIによって自動化できるようになったためです。
具体的には、AIチャットボットが24時間365日、社員からの基本的な質問に答えたり、システムの異常を検知して一次対応を自動で行ったりする事例が増えています。
これにより、「ただ運用するだけ」の仕事は、今後ますますAIに奪われていくでしょう。

波3:クラウド化の進展 -「所有」から「利用」へ
物理サーバーを自社で持たない「クラウド3化」の流れが、インフラ担当としての社内SEの役割を大きく変えました。
なぜなら、AWSやAzureのようなクラウドサービスを利用すれば、企業は自前でデータセンターを構築・管理する必要がなくなるからです。
サーバーの設置、配線、温度管理、物理的な障害対応といった、かつてのインフラ担当者の主な仕事は、クラウドベンダーの仕事になりました。
このように、インフラの「所有」から「利用」へのシフトが、従来のインフラ系社内SEの仕事を過去のものにしつつあるのです。
それでも「社内SEが絶対に必要」な4つの理由
ここまでの話で、不安が大きくなったかもしれません。しかし、ここからが本題です。これらの時代の波は、旧来の仕事を奪う一方で、社内SEにしか担えない、より重要で新しい役割を生み出しているのです。

株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)の調査によると、国内企業の約8割が「IT人材の不足」を実感しており、特に「情報セキュリティ」や「ITインフラ」を担う人材が足りていない、という結果が出ています。
(出典:IIJ「国内企業のIT活用実態調査」)
つまり、「社内SEはいらない」どころか、実際にはほとんどの企業で社内SEが足りていないのが現実なのです。
理由1:乱立するSaaSを束ねる「まとめ役」が必要だから
結論として、各部署がバラバラに導入したSaaSを、全社最適の視点で統制する「まとめ役」の役割が、新たに求められています。
なぜなら、放置すれば、データが部署ごとにバラバラに保管されたり(サイロ化)、セキュリティレベルが統一されていなかったりと、かえって非効率で危険な状態に陥ってしまうからです。
例えば、全社員のアカウント情報を一元管理し、入退社時の設定を自動化する。部署ごとに契約しているSaaSのライセンスを見直し、無駄なコストを削減する。こうしたIT環境全体の交通整理ができるのは、社内SEしかいません。
この全体を俯瞰するガバナンス能力こそ、これからの社内SEの価値となります。



理由2:ビジネスとITを繋ぐ「翻訳家」が必要だから
現場の業務を深く理解し、ITソリューションをビジネスの価値に繋げる「翻訳家」は、外部の人間には決して務まりません。
その理由は、外部ベンダーは、企業の文化や部門間の力学といった、目に見えない「行間」を読むことができないからです。
社内SEは、現場の担当者との信頼関係を基に、彼ら自身も気づいていない潜在的な課題を発見し、最適なSaaSの活用法を提案することができます。
この「業務理解」に基づいた提案力こそが、社内SEの揺るぎない存在価値です。

理由3:新技術を導入する「戦略家」が必要だから
AIや新しいSaaSを「使う側」ではなく、どの技術をどう導入すれば自社の競争力が高まるかを判断する「戦略家」が不可欠です。
なぜなら、技術の進化はあまりに速く、経営層だけでは、どの技術に投資すべきか、そのリスクは何かを判断できないからです。
例えば、生成AIを導入する際、単にツールを提供するだけでなく、社内向けの利用ガイドラインを策定したり、社員研修を企画したり、費用対効果を検証したりする。こうした一連のプロセスを主導できるのが社内SEです。
この技術的な目利きと戦略的視点こそ、未来の社内SEに求められる中核的な能力です。
理由4:ITガバナンスとセキュリティを守る「最後の砦」が必要だから
結論として、クラウド化やSaaS導入が進むほど、情報セキュリティやITガバナンス4の全体責任を負う「最後の砦」の重要性は増していきます。
その理由は、外部に全てを委託することは、企業の根幹に関わるセキュリティポリシーや法的責任までを丸投げすることになり、あまりにリスクが高いからです。
全社的なセキュリティポリシーを策定し、従業員のITリテラシー教育を実施し、万が一インシデントが発生した際に最終的な対応責任を負う。この役割は、社内の事情に精通し、信頼されている社内SEだからこそ担える、決してなくならない仕事です。
企業の根幹を守るという、この重要な役割が社内SEにはあるのです。


【キャリア戦略】AI時代に価値が爆上がりする社内SEの3つの条件
では、これからの時代に「絶対に必要とされる社内SE」になるためには、何をすべきなのでしょうか。あなたが目指すべき3つの条件を具体的にお伝えします。
条件1:ビジネス課題を「発見」できる
言われたことをやるだけでなく、自らビジネス課題を発見し、解決策を提案できる能力です。
なぜなら、AIにできるのは「与えられた問いに答えること」であり、「そもそも何を問うべきか」を発見することはできないからです。
現場の業務に入り込み、「もっとこうすれば効率化できるのに」「このデータを活用すれば新しいサービスが生まれるかもしれない」といった課題やチャンスの「種」を見つけ出す。この能力が、あなたの価値の源泉となります。
条件2:プロジェクトを「推進」できる
発見した課題を、実際にプロジェクトとして形にし、完遂させる能力です。
その理由は、どんなに素晴らしいアイデアも、実現しなければ価値を生まないからです。
経営層を説得して予算を獲得し、関連部署を巻き込んで協力を取り付け、外部ベンダーを適切に管理する。こうした人を動かし、物事を前に進める力は、AIには決して真似のできない、人間ならではのスキルです。
条件3:テクノロジーを「評価」できる
次々と登場する新しい技術やSaaSについて、その本質的な価値と自社への適合性を冷静に見極める「目利き力」です。
なぜなら、世の中には過剰な宣伝文句や、見せかけだけのツールも溢れているからです。
流行に流されることなく、「この技術は、本当に自社の課題を解決するのか?」「導入コストに見合うリターンはあるのか?」を客観的に評価し、最適なツールを最適なタイミングで選択する。この冷静な判断力が、企業の無駄なIT投資を防ぎます。
まとめ:未来は、変化を歓迎する者のためにある
「社内SEはいらない」という言葉の裏にある、本当の意味を解説してきました。
- 「いらない」と言われる理由:SaaSやAIの普及で、旧来の「システムの守り番」としての役割が減少したため。
- それでも「必要」な理由:IT環境が複雑化する中で、「まとめ役」「翻訳家」「戦略家」といった、より高度な役割の重要性が増しているため。
- 未来の社内SE像:ビジネス課題を発見し、プロジェクトを推進し、テクノロジーを評価できる「企業の変革パートナー」。
- 結論:「社内SE不要論」は、変化を恐れる者にとっては「時代の終わり」を、変化を歓迎する者にとっては「最高の時代の幕開け」を意味する。
あなたの目の前には、単なるIT担当者から、企業の未来を創る主役へと進化する、エキサイティングな道が拓けています。その変化の波に乗り、自らの価値を再定義してください。未来は、あなたのような挑戦者を待っています。
自分の市場価値を再定義し、未来のキャリアを考えたいあなたへ
「これからの時代に評価されるスキルって何だろう?」「自分の経験を活かせる、もっと戦略的な仕事はないだろうか?」――そんな風に、未来のキャリアを考え始めたあなたへ。
あなたのスキルや経験を新しい視点で評価し、DX推進やIT戦略など、これからの時代に求められるポジションを紹介してくれる、社内SEの転職に本当に強い転職エージェントだけを厳選して比較した記事をご用意しました。
>>【失敗しない】社内SE転職エージェント選び|おすすめ12社を比較
そもそも転職活動の進め方から不安な方は、こちらの記事で全体像を掴んでください。
FAQ:「社内SE不要論」についてよくある質問
Q1. とは言え、本当に仕事がなくなることはありませんか?
A1. 「何もしなければ」仕事がなくなる可能性はあります。PCの設定やパスワードリセットのような単純作業は、今後ますます自動化されるでしょう。しかし、本記事で解説したような「ビジネス課題の発見」や「プロジェクト推進」といった、より創造的で戦略的な仕事がなくなることは、当面考えられません。
Q2. 30代後半・40代からでも、新しい社内SE像を目指せますか?
A2. もちろんです。むしろ、これまでの業務で培ってきた「業務知識」や「社内外の調整経験」は、若い世代にはない大きな武器になります。技術トレンドを学び直す意欲さえあれば、年齢はハンデではなく、むしろ強みになります。
Q3. 今の会社にいても、未来の社内SE像になれる気がしません。
A3. 残念ながら、経営層のITへの理解が乏しい会社では、個人の努力だけでは限界があるかもしれません。その場合は、この記事で解説したようなスキルを意識して磨きつつ、あなたの価値を正当に評価してくれる「DXに積極的な企業」や「IT部門に裁量がある企業」への転職を、本格的に検討するタイミングかもしれません。
Q4. 具体的に、まず何から勉強すれば良いですか?
A4. まずは、自社の「中期経営計画」や「決算説明資料」を読み込むことをお勧めします。自社がどこに向かおうとしているのか、どんな課題を抱えているのかを知ることが、全てのスタートです。その上で、その課題を解決できそうなクラウドサービス(SaaS)の事例を調べたり、データ分析の入門書を読んでみたりすると良いでしょう。
Q5. 結局、一番大事なことは何ですか?
A5. 「自分は単なるIT担当者ではない」という意識を持つことです。「自分は、ITという武器を使って、会社のビジネスを前に進めるパートナーなんだ」という当事者意識を持つこと。その意識が、あなたの行動を変え、学びを変え、そして未来のキャリアを変えていきます。
この記事で使われている専門用語の解説
- 1. SaaS (サース)
- Software as a Serviceの略。利用者がソフトウェアを自身のコンピュータにインストールするのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態。Microsoft 365やSalesforceなどが代表例。
- 2. AI (エーアイ)
- Artificial Intelligence(人工知能)の略。人間の知的活動をコンピュータで模倣したもの。データの学習を通じて、予測、分類、言語処理などを行うことができる。
- 3. クラウド
- インターネットなどのネットワーク経由で、サーバー、ストレージ、ソフトウェアといったITリソースを利用する形態のこと。自社で物理的な機器を保有・管理する必要がないのが特徴。
- 4. ITガバナンス
- 企業がIT戦略を適切に策定・実行し、その効果やリスクを管理・統制するための仕組みのこと。IT投資の最適化や、情報セキュリティの確保などを目的とする。
- 5. SSO (エスエスオー)
- シングルサインオンの略。一度のユーザー認証で、連携する複数のクラウドサービスやアプリケーションにログインできるようにする仕組み。利便性向上とセキュリティ強化に繋がる。
- 6. DX (デジタルトランスフォーメーション)
- デジタル技術を活用して、企業のビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などを根本的に変革し、競争上の優位性を確立すること。単なるIT化ではなく、変革を目的とする。