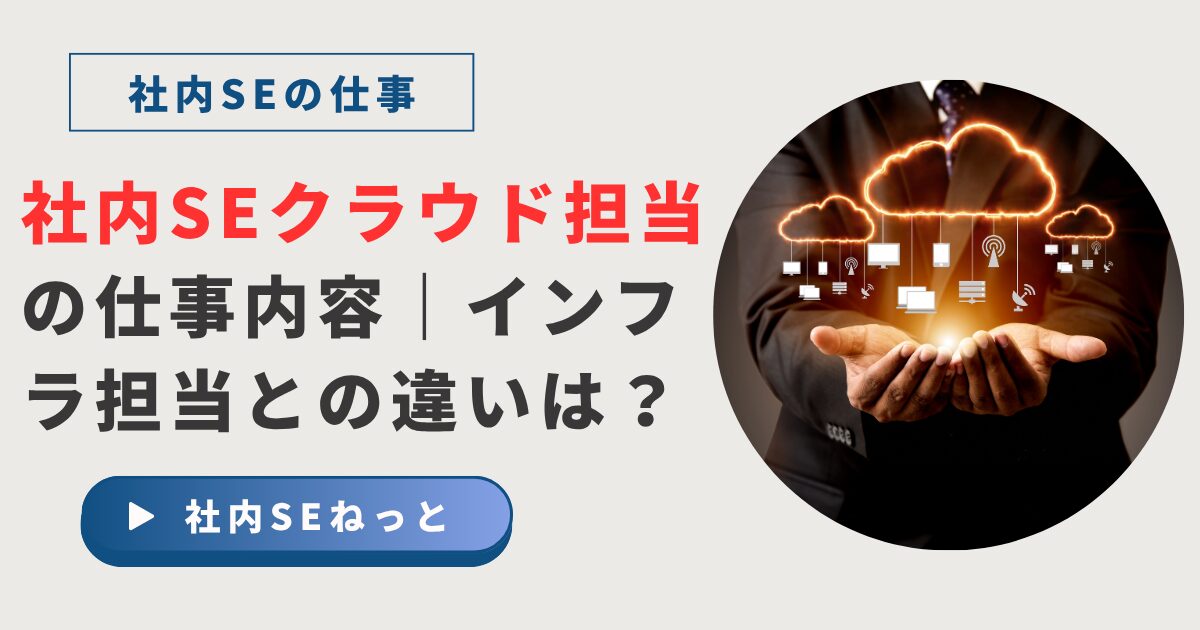「AWSやAzureの知識は必須?オンプレミスの経験だけじゃダメかな…」
「クラウドエンジニアっていうと専門職っぽいけど、社内SEだとどう違うの?」

デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の重要課題となる中、「社内SEのクラウド担当」、あるいは「社内クラウドエンジニア」という役割への関心が急速に高まっています。
しかし、その具体的な仕事内容は、従来のインフラ担当とどう違うのか、どこまで専門的な知識が求められるのか、実態が見えにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、社内SEの「クラウド担当」という、今最も熱い仕事に焦点を当て、20年の現場経験を持つ私が、その具体的な仕事内容から求められるスキル、キャリアパスまで、リアルな視点で網羅的に解説します。
この記事を読めば、こんな疑問が解決します!
- 社内クラウド担当の戦略的な役割と具体的な仕事内容
- 従来のインフラ担当との決定的な違い
- IaC、FinOps、SREといったモダンな運用手法との関わり
- クラウド担当に求められる専門スキルとキャリアパス
社内クラウド担当の役割とインフラ担当との違い
インフラ・セキュリティ・クラウド担当の全体像と比較
この記事では「クラウド担当」の仕事に絞って深掘りしますが、他の技術職(インフラ、セキュリティ)との違いや連携について知りたい方は、まずはこちらのまとめ記事からご覧いただくのがおすすめです。
「クラウド担当って、要はインフラ担当がクラウドを触るだけでしょ?」
そう思われがちですが、実は全くの別物です。IT基盤を支える点は同じでも、そのミッションとアプローチは大きく異なります。まずは、その決定的な違いから見ていきましょう。
クラウド担当の定義:ビジネスを加速させる専門家
社内クラウド担当者は、クラウドサービスの設計・実装・管理・最適化に特化した専門職です。彼らは単なる技術者ではなく、クラウド戦略を企業のビジネス目標と結びつけ、事業のスピードや革新を後押しする重要な役割を担います。
SaaS、PaaS、IaaSといった各種クラウドサービスの特性を深く理解し、ビジネスニーズに最適な組み合わせを提案する能力が、彼らをビジネスに不可欠な存在へと押し上げます。
インフラ担当との決定的な違いはココ!
両者の違いを3つのポイントに絞って解説します。
- 焦点の違い:物理から仮想・自動化へ
インフラ担当が物理サーバーやネットワーク機器といった「モノ」の管理に注力するのに対し、クラウド担当の焦点は仮想化されたリソースやAPI、そして自動化技術にあります。物理的な機器操作よりも、コードによるインフラ管理が業務の中心となります。 - コスト意識の違い:資産管理からFinOpsへ
インフラ担当が物理資産の購入・維持といった「資産管理」の視点でコストを考えるのに対し、クラウド担当は利用量に応じて変動する費用をリアルタイムに監視・最適化する「FinOps」1の視点が不可欠です。 - アプローチの違い:事後対応から事前設計へ
インフラ担当が障害発生後の対応に追われがちな一方、クラウド担当は信頼性の高いシステム設計や自動復旧の仕組みを構築するなど、障害を未然に防ぐプロアクティブな活動が中心となります。

クラウド担当の具体的な仕事内容【戦略から最適化まで】
「じゃあ、具体的には毎日どんなことをしているの?」
クラウド担当の業務は実に多彩です。ここでは、その多岐にわたる業務を5つのカテゴリーに分け、具体的なアクションと共に深掘りしていきます。あなたのイメージする仕事がきっと見つかるはずです。
クラウド戦略立案とサービス選定
ビジネスの目標達成に向けて、どのクラウドを、どのように使うかという最も上流の設計を担当します。
- ビジネスニーズの評価と解決策の提案:各部門の課題をヒアリングし、IaaS、PaaS、SaaSといったクラウドサービスをどう組み合わせれば解決できるかを提案します。
- 主要クラウドの比較検討:AWS、Azure、GCPなどの特徴を理解し、コスト、機能、セキュリティなどを総合的に比較して、自社に最適なサービスを選定します。
クラウド環境の設計・構築と自動化
戦略が決まったら、実際にクラウド上にシステムを構築します。手作業を極力減らし、コードでインフラを管理するのが現代のクラウド担当の腕の見せ所です。
- クラウドアーキテクチャ設計:システムの規模やアクセス数に応じて柔軟に拡張でき、障害にも強いクラウドネイティブな構成を設計します。
- Infrastructure as Code (IaC)の実践:TerraformやCloudFormationといったツールを使い、サーバーやネットワークの設定をコードで管理します。これにより、手作業によるミスを防ぎ、迅速かつ再現性の高い環境構築を実現します。IaC8はクラウド担当のコアスキルと言えるでしょう。
- 開発プロセスの支援 (CICD):開発チームと連携し、アプリケーションの変更を迅速かつ安全にリリースするためのCICD2パイプラインの構築を支援することも重要な役割です。
クラウドセキュリティとガバナンス
手軽に利用できるクラウドだからこそ、セキュリティの確保と統制は非常に重要です。


クラウドコスト最適化(FinOps)
使った分だけ費用が発生するクラウドの特性を理解し、無駄なコストを削減して投資対効果を最大化します。
- 利用料の監視と分析:クラウドの利用状況とコストを詳細に監視・分析し、「どのサービスに」「どれだけ費用がかかっているか」を可視化します。
- コスト削減戦略の策定と実行:分析結果に基づき、不要なリソースの停止、適切なサーバーサイズへの変更(ライトサイジング)、予約割引の活用など、具体的なコスト削減策を提案・実行します。

SRE原則の導入と信頼性の追求
ただ動くだけでなく、「止まらない」「遅くない」といったシステムの信頼性をデータに基づいて科学的に追求します。
クラウド担当に求められる専門スキルセット
「よし、仕事内容は分かった。じゃあ、自分には何が必要なんだろう?」
そう思いますよね。クラウド担当として活躍するには、従来のインフラ知識に加え、クラウド特有の専門知識や新しい技術への対応力が不可欠です。ここでは、特に重要なスキルを厳選して紹介します。
① テクニカルスキル
- 主要クラウドプラットフォームの知識:AWS、Azure、GCPといった主要クラウドのコアサービス(コンピューティング、ストレージ、ネットワーク等)や料金体系に関する専門知識は、全ての土台となります。
- IaCと自動化スキル:TerraformやCloudFormationといったツールや、Python等のスクリプト言語を用いたインフラ自動化スキルが求められます。
- コンテナ技術(Docker/Kubernetes):アプリを動かす「魔法のお弁当箱」であるDockerと、その司令塔であるKubernetesを使いこなすスキルは、今や必須と言っても過言ではありません。
- サーバーレスアーキテクチャ:サーバー管理を意識せずにアプリを実行するAWS LambdaなどのFaaSを活用し、コストを抑えつつ柔軟な仕組みを設計する能力が求められます。
- クラウドネイティブなセキュリティとネットワーク:IAMによる権限管理、WAFによるアプリケーション保護、VPCによる仮想ネットワーク構築などを深く理解し、設計・実装できるスキルが必要です。
② クラウド担当として特に重要なヒューマンスキル
- ビジネス理解力とコミュニケーション能力:複雑なクラウド技術やコスト構造を、非技術者に分かりやすく説明し、納得してもらうために不可欠です。
- 高度な問題解決能力:原因が多岐にわたる複雑なクラウド上の問題を論理的に切り分け、解決に導く能力が求められます。
- 継続的な学習意欲:日進月歩で進化するクラウド技術に追随し、常に最適な構成を模索し続ける探求心が何よりも重要です。
クラウド担当のキャリアと将来性
「クラウド担当になった後、どんなキャリアが描けるんだろう?」
心配いりません。クラウドスキルを持つ専門家の需要は非常に高く、将来性豊かなキャリアパスが拓かれています。
やりがいの源泉:ビジネス変革への貢献
最大のやりがいは、クラウドという最新技術で、自社のビジネス変革や新サービス創出に直接貢献できる点です。自分の仕事が会社の成長に直結していると実感できるのは、何物にも代えがたい喜びです。
乗り越えるべき壁:絶え間ない学習とコスト管理
一方で、技術の進化が非常に速いため、継続的な学習が不可欠である点や、利用料が変動するため常にコスト管理のプレッシャーがある点は大変な部分と言えるでしょう。
多彩なキャリアパス
クラウド担当として経験を積むことで、以下のような市場価値の高い専門職を目指せます。
- クラウドアーキテクト:企業全体のクラウド戦略に基づき、最適なシステム全体の設計を行う専門家。
- SRE (Site Reliability Engineer):システムの信頼性、可用性、パフォーマンス向上を専門的に担当するエンジニア。
- DevOpsエンジニア:開発と運用の連携を強化し、CICDを通じて迅速なサービス提供を実現する専門家。
- クラウドセキュリティスペシャリスト:クラウド環境に特化したセキュリティ対策の専門家。

まとめ:企業の未来をクラウドで切り拓く専門家
ここまで、社内SEの「クラウド担当」について、その戦略的な役割から具体的な仕事内容、スキル、キャリアまでを解説しました。
クラウド担当は、単にクラウドサービスを運用するだけでなく、企業のビジネス戦略とITを結びつけ、事業成長を加速させる極めて専門性の高い役割です。従来のインフラ管理とは異なる新しいスキルや考え方が求められますが、その分、大きなやりがいと成長機会が得られる職種と言えるでしょう。
社内SEへの転職を具体的に考え始めたあなたへ
社内SEというキャリアに興味が湧いたら、次はいよいよ具体的な転職活動の準備です。でも、「何から始めればいいの?」「自分に合う転職エージェントは?」と迷ってしまいますよね。
そんなあなたのために、転職の成功確率をグッと上げるための記事を2つご用意しました。ご自身の状況に合わせて、ぜひご覧ください。
FAQ:「社内SEのクラウド担当」についてよくある質問
Q1. 社内クラウド担当とIT企業のクラウドエンジニアの主な違いは何ですか?
A1. 最も大きな違いは「誰のために、何を目的とするか」です。IT企業のエンジニアは、多くの場合、顧客企業に対してクラウドシステムを構築・提供します。一方、社内クラウド担当は、自社のビジネス目標達成のために、自社内のシステムやサービスにクラウド技術を最適に活用することが目的となります。
Q2. AWS、Azure、GCPの全ての知識が必要ですか?
A2. 全てに精通している必要はありません。まずは自社が利用している、あるいは導入を検討しているクラウドの知識を深めることが重要です。ただし、複数のクラウドを使い分ける(マルチクラウド)企業も増えているため、複数のクラウドへの基本的な理解や学習意欲は高く評価されます。
Q3. オンプレミスのインフラ経験しかなくても転職できますか?
A3. はい、可能性は十分にあります。オンプレミス環境のサーバーやネットワークの知識は、クラウドを理解する上で重要な基礎となります。特にオンプレミスからクラウドへの移行プロジェクトでは、両方の知識を持つ人材が重宝されます。資格取得や自主学習でクラウドへの適応力をアピールすることが大切です。
Q4. プログラミングスキルも必要になりますか?
A4. 必須ではありませんが、IaCの実践や運用の自動化のために、PythonやPowerShellといったスクリプト言語のスキルが求められることが増えています。習得しておくと業務の幅が大きく広がります。
この記事で使われている専門用語の解説
- 1. FinOps(フィンオプス)
- Financial Operationsの略。クラウドの財務管理手法のこと。技術、ビジネス、財務の各チームが連携し、データに基づいてクラウド費用を管理・最適化することで、ビジネス価値を最大化する考え方。
- 2. CICD
- Continuous Integration/Continuous Delivery(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)。ソフトウェアのビルド、テスト、リリースといったプロセスを自動化し、開発サイクルを高速化する手法。
- 3. IAM (Identity and Access Management)
- 適切なユーザーが必要なリソースにのみアクセスできるように、ユーザー認証とアクセス権限を管理するセキュリティの仕組み。
- 4. WAF (Web Application Firewall)
- ウェブアプリケーションファイアウォール。ウェブアプリケーションを標的としたサイバー攻撃(SQLインジェクションなど)を検知・防御するセキュリティ対策。
- 5. SLI (Service Level Indicator)
- サービスレベル指標。システムのパフォーマンスを定量的に測定するための指標。例えば、可用性(稼働率)やレイテンシー(応答時間)など。
- 6. SLO (Service Level Objective)
- サービスレベル目標。SLIに対して設定される具体的な目標値。例えば、「月間可用性99.9%」など。
- 7. SRE (Site Reliability Engineering)
- サイト信頼性エンジニアリング。Googleが提唱した、システムの信頼性と運用効率を向上させるためのアプローチ。ソフトウェアエンジニアリングのプラクティスを運用業務に適用する。
- 8. IaC (Infrastructure as Code)
- インフラストラクチャ・アズ・コード。サーバーやネットワークといったインフラの構成を、コードを用いて記述・管理する手法。手作業によるミスをなくし、インフラ構築の再現性と効率性を高める。